紫蘇は毎年こぼれ種で増える植物ですが、年回りによっては発芽が悪く紫蘇の収穫量が少なくなってしまうこともあると思います。
そんなときは、発芽した紫蘇を使って株を増やしてみましょう。
この記事では、紫蘇の株を増やすおすすめの方法を詳しく解説しているのでぜひ参考にして下さいね。
紫蘇(シソ)の特徴
| 一般的な呼び名 | 紫蘇 |
| 別名 | イヌエ(古名) |
| 和名 | しそ |
| 英名 | Perilla(ぺリラ) |
| 学名 | Perilla frutescens var. crispa |
| 分類 | シソ目・シソ科・シソ属 |
| 形態 | 芳香性の一年草 |
| 大きさ | 50cm~80m |
| 開花時期 | 9月~10月 |
| 原産国 | 中国 |
| 日当り環境 | 半日陰 |
| 耐寒性 | 冬に枯れる |
| 耐暑性 | 強い |
紫蘇が日本で栽培され始めた歴史はとても古く、平安時代には本格的に栽培がおこなわれていたとされています。
遠い昔から生育している植物なので、それだけでも日本の土地や気候との相性が良いことが分かると思います。
紫蘇は口当たりが気にならない柔らかい葉質なうえ、爽やかな香りが楽しめるので様々な料理に使用されます。
生育も旺盛で、葉を多少収穫しても次々に脇芽を付けて成長するため株数が増えると食べきれないほど収穫できますよ。どうやって処理するか悩んでしまう方も多いようです(笑)
紫蘇(シソ)をシーズン中に増やすなら挿し木・水挿しがおすすめ

紫蘇は秋に種を作るので、翌年になると地面にこぼれた種から発芽して自然に繁殖する植物ですが、もし翌年の発芽が悪かった場合は、『挿し木』または『水挿し』で増やすのが簡単でおすすめですよ。
紫蘇はこぼれ種で増やそうとすると繁殖し過ぎてしまって他の植物の生育に影響を与える可能性もあるので、はじめから種をつける株を制限して、翌年挿し木や水挿しで株を増やす考え方も良いと思います。
種以外でも増やす方法があることを知っておいてくださいね。
紫蘇の挿し木・水挿しの方法を解説



ここからは実際に紫蘇を挿し木・水挿しする手順と方法について解説しています。
挿し木する前に準備するもの
・挿し穂
・植木鉢
・挿し木用の土(赤玉土など肥料分が含まれていない新しいもの)
・よく切れるハサミ
・割りばしなどの棒(挿し穂を土に刺す時の穴あけ用)
挿し木の手順
紫蘇を挿し木にする場合は、以下の手順で行えば簡単です。
- 紫蘇の親株から挿し穂を採取する(硬化した茎が良いです)
- 水を張った容器に挿し穂を入れて水上げする(約1時間)
- 挿し木用の土に水やりをしてあらかじめ湿らせておく
- 細い棒を使って挿し穂を挿し込むための穴をあけておく
- 挿し穂の切り口部を傷めないように用土に挿し入れ、そっと土を寄せる
- 挿し穂がグラつかないように根元付近の土に圧をかける
ここまで準備ができたら最後に水やりをして、直射日光の当たらない明るい日陰に保管しておきましょう。
生育温度が保たれていれば、だいたい1ヶ月程度で発根します。新芽が出てくれば発根するサインなのでさらに1週間ほど経過したあと鉢上げするようにしましょう。
水差し(水挿し)で準備するもの
ここでは紫蘇を水挿しで発根させるために準備するものを紹介します。
・透明なコップなどの容器
・よく切れるハサミ
挿し穂を水の中にそのまま長期間置いておくので、発根の状態が見える透明な容器を準備しましょう。
透明な容器を使用すると水の汚れ具合が分かるので水の交換時期が分かり易いのでおすすめですよ。水が腐敗すると挿し穂も腐ってしまうので水の管理は必須と言えます。
水差し(水挿し)の手順
- 紫蘇の親株から挿し穂を採取する
- 水を入れた容器に挿し穂を入れて、直射日光の当たらない明るい日陰に保管
- 水が汚れたら定期的に交換する
あとは水を清潔に保つようにこまめに交換してあげれば約1ヶ月程度で白い根が生えてきますが、しっかり根が伸びてくるまでは土植えにしない方が良いです。
水差しで出た根は土植えへの環境の変化にすぐに対応できないため、水を吸い上げることが上手にできません。
そのため、根が少し伸びた程度で土植えしてしまうと、根から養分や水分が吸収できずに枯らせてしまう可能性があります。
まとめ
今回の記事では紫蘇の増やし方について解説しました。
紫蘇はこぼれ種で自然に増える繁殖力の強い植物ですが、翌年芽吹いた紫蘇を挿し木することでさらに株を増やすことができます。
水挿しだと水に茎をつけておくだけで発根してくれるのでとてもお手軽ですよ。
興味があればぜひ試してみて下さいね。
紫蘇の関連記事

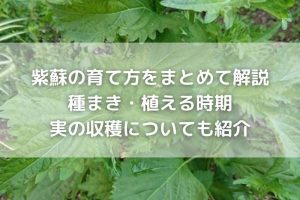
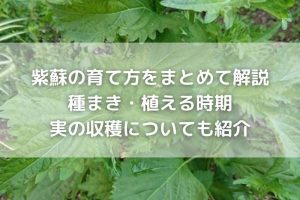


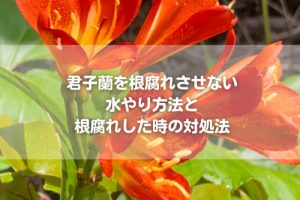



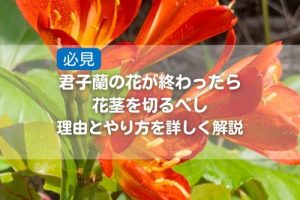

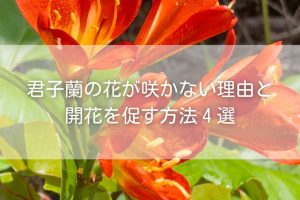


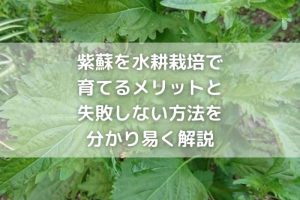

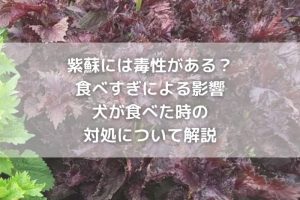

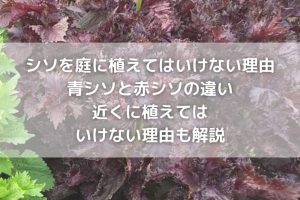
コメント