紫蘇は日本ハーブの代表格とも言うべき、日本の食卓では無くてはならない食材ですよね?
料理への香味付けのために、プランターや庭のちょっとしたスペースに育てている方も多いのではないでしょうか。
でも中には『紫蘇を庭に植えないほうが良い』と言われる方もいるんですよね。なぜなのでしょう?
今回の記事では紫蘇を地植えしない方が良いとされる理由について詳しく解説しています。
また、青シソと赤シソを混在して育ててはいけないとされる理由についても合わせて紹介しているので、ぜひ参考にしてくださいね。
紫蘇(シソ)の特徴
| 一般的な呼び名 | 紫蘇 |
| 別名 | イヌエ(古名) |
| 和名 | しそ |
| 英名 | Perilla(ぺリラ) |
| 学名 | Perilla frutescens var. crispa |
| 分類 | シソ目・シソ科・シソ属 |
| 形態 | 芳香性の一年草 |
| 大きさ | 50cm~80m |
| 開花時期 | 9月~10月 |
| 原産国 | 中国 |
| 日当り環境 | 半日陰 |
| 耐寒性 | 冬に枯れる |
| 耐暑性 | 強い |
紫蘇が日本で栽培され始めた歴史はとても古く、平安時代には本格的に栽培がおこなわれていたとされています。
遠い昔から生育している植物なので、それだけでも日本の土地や気候との相性が良いことが分かると思います。
紫蘇は口当たりが気にならない柔らかい葉質なうえ、爽やかな香りが楽しめるので様々な料理に使用されます。
生育も旺盛で、葉を多少収穫しても次々に脇芽を付けて成長するため株数が増えると食べきれないほど収穫できますよ。どうやって処理するか悩んでしまう方も多いようです(笑)
紫蘇(シソ)を庭植えしてはいけないとされる2つの理由と対策

ここからは紫蘇を庭植えしてはいけないと言われる主な2つの理由について解説します。
- こぼれ種で次々に繁殖するから
- 紫蘇につく害虫が多いから
1|こぼれ種で次々に繁殖するから
紫蘇は1年草で秋になると種を作り、気温の低下とともに枯れていく植物です。
秋にこぼれる種が翌年の春に芽吹くため、思いもよらない場所から紫蘇が生えてくるケースが多く…
シソが増えすぎて困る!
他の植物の園に生えてきて抜くのが面倒・・・
紫蘇を育てている方の中にはこのような声も多いです。
とはいえ対策としては単純明快で、花が出てきたら摘み取るようにすれば勝手に増殖することは無くなります。
翌年分の種を採取する場合も、事前に採取する株を幾つか決めておいて残りの花や実は摘み取るようにすると管理もしやすいのでおすすめですよ。
紫蘇を増やしたくなければ花を摘み取る。実をつけさせないよう管理しましょう。
2|紫蘇につく害虫が多いから



紫蘇は日本のハーブとも呼ばれる香りの強い植物ですよね。
そのため多くの害虫は臭いを嫌い近寄らないのですが、中には紫蘇の葉を好んで食べにくる害虫も多いんです。
- ハスモンヨトウ【蛾の幼虫】
- ベニフキノメイガ【蛾の幼虫】
- ヨモギエダシャク【蛾の幼虫】
- ミツモンキンウワバ【蛾の幼虫】
- バッタ類
主に蛾の幼虫が好むため紫蘇が群生している場所には、それらの幼虫が集まりやすくなります。
同じくバッタも紫蘇の葉が好きなようで、通常ではあり得ないほどの数のバッタが紫蘇の葉の上に乗っていたりもします。
どの害虫も紫蘇を食べるので食害による影響も大きいですが、虫が苦手な人にとっては庭先にこれらの虫が集まっていることが問題と考える人も多いです。
そんな理由から『紫蘇を庭先に植えてはいけない』と言われるようになったとされています。
対策としては、紫蘇をあまり広範囲に育て過ぎないのがポイントと思います。
自家栽培で農薬を使いたいという方は少ないと思いますし、食害されても完全にシソが収穫できないという訳でもないので、害虫が群生しないように紫蘇の数も調整してあげるのが一番だと思います。
栽培場所をコンパクトにしておけば、ネットを被せるなどの対策もしやすいので管理しやすいように栽培エリアを決めてみましょう。
青シソと赤シソの違いについて
紫蘇は大別すると『青シソ』と『赤シソ』に分けられますが、細かく見ていくとその中にも多数の品種が存在しています。
青シソと赤シソの違いをまとめみました。
| 違い | 青シソ | 赤シソ |
|---|---|---|
| 葉の色 | 緑色 | 赤色 |
| 香り | 強い | 弱い |
| 流通期間 | 一年中流通 | 5月~7月 |
| 用途 | 刺身のツマ・てんぷら | しそジュース・うめぼし・しば漬け |
| 若芽を摘んだものが『大葉』 |
青シソは香りを活かした薬味として用いられることが多いですが、赤シソは食用というよりも赤い色味を使った用途が多いですね。
基本的にはどちらも特性自体は同じなので、食卓で使いたいものを育てるのがおすすめです。
青シソと赤シソを同じ場所に植えてはいけない理由
青シソと赤シソを両方自宅で育てたいという方は多いと思いますが、1つだけ注意すべきポイントがあるので事前に知っておきましょう。
青シソと赤シソは同じ場所で植えないように注意が必要なんです。
その理由は2種類の異なるシソ同士が受粉して交配してしまうから。
別々のシソが交配すると以下のようなデメリットがあります。
- 葉が赤と緑の混ざった色になってしまう
- 香りが弱まってしまう
- 繁殖力が強くなる
- 元の品質の良いシソが無くなる
青シソと赤シソをイイとこどりしてくれたら最高なんですが、結果としてはとても中途半端な品質のシソが増殖してしまいます。
味や香りが悪くなるばかりか生命力や繁殖力だけが強くなるため、葉質が硬くなり種で繁殖する数も多くなります。
品質が悪くなったものは、そのまま置いておいても改善することは無いのでいったん駆逐して新たな苗や種を植え付けて育てなおすようにしましょう。
交配しないように種を作らせなければOK
2種が交配して低品質なシソが繁殖しないように、家庭で赤シソと青シソを育てる場合は場所を離して栽培するようにしましょう。
また、先ほどの繁殖させないための方法と同じように、青シソと赤シソを交配させないためには花を摘み取ってしまう方法がベストです。
繁殖させるつもりが無いのであれば花や実を見つけ次第、摘み取る管理を行いましょう。
まとめ
今回はシソを庭植えしてはいけない2つの理由と赤シソ・青シソに関する情報をまとめて解説しました。
- シソはこぼれ種で増殖しやすいので花や実の管理が重要
- 特定の害虫が集まりやすいので栽培場所の範囲をコンパクトにする
- 青シソと赤シソは交配させると低品質なシソが増殖する
食卓でちょっと必要な時に利用できるシソは、家庭菜園では重宝される食材です。
きちんと管理していれば、繁殖し過ぎてしまったり、交配させてしまうことは少ないと思うので、ぜひ日々の管理を行いながらシソの育成を楽しんでくださいね。
紫蘇の関連記事

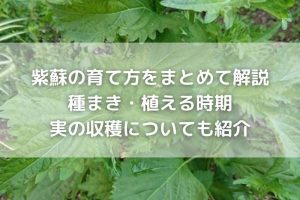
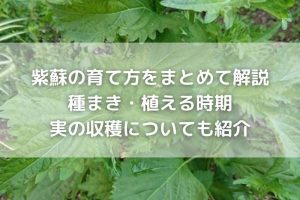


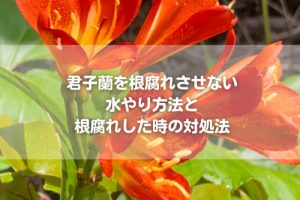



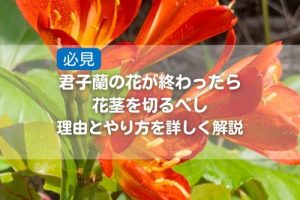

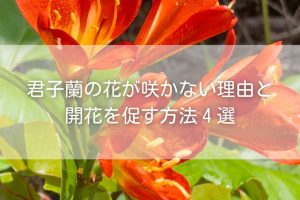


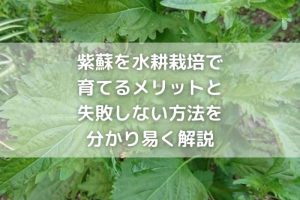

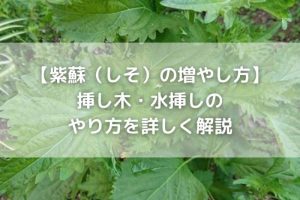

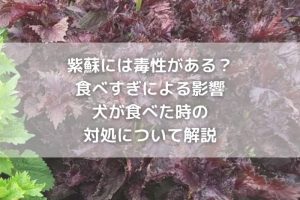
コメント