お彼岸の頃になるとよくみかけるヒガンバナ。
花が咲いている時には葉や茎などが一切なく、強く反り返った花だけが頂部に咲くというとても特徴的な植物ですよね。
実はこのヒガンバナには毒があるとされています。子供のころ路地に咲くヒガンバナを触ってはいけないと親から言われたことがある方も多いのではないでしょうか?
でも実際にはどのくらいの毒性があって、どの程度の危険性なのかが分からないと思います。
そこでこの記事では
- ヒガンバナとはどんな植物か
- ヒガンバナの毒性について
ヒガンバナはどんな植物?

ヒガンバナは、秋の彼岸(9月)の頃に鮮やかな花を咲かせたあと、その年の秋の終わりに葉が伸びて翌年の初夏に枯れるという、ちょっと変わった育成パターンを持つ多年草です。
中国が原産地で、現在は国内全国各地の田んぼのあぜ道や道端で見られるようになりました。
ヒガンバナの毒性について



ヒガンバナには『リコリン』という毒成分が含まれている有毒植物です。
花・茎・葉・球根などすべての部位に毒性分を含んでいますが、一番気を付けるべきは鱗茎(りんけい)と呼ばれる球根部分になります。
万が一、誤って口にしてしまうと嘔吐や下痢といった消化器系の症状を起こすこともあるので注意が必要です。
どの程度の毒性なの?
ヒガンバナに毒があるといっても、人間に対しては大量に摂取しない限り致死量になることはないので安心して下さい。
約10gのリコリンを摂取しなければ致死量にはならず、それはヒガンバナの球根を数百個単位で食べないと達成することのできない数値。なので基本的にヒガンバナを食べたことによって人の生命に危険を及ぼすことはまずないと思って良いです。
ヒガンバナのペットへの影響



人間に対しての致死量にはならなくてもペットなどの小動物に対しては気をつけた方が良いです。
もともとヒガンバナは墓地を荒らすネズミやモグラから墓地や農作物を守るために、ヒガンバナの毒性を利用し周辺に植えたとも言われています。
体の小さな動物はヒガンバナの球根たった1つでも充分致死量に達するので、ペットを飼っている方は管理方法や散歩道への配慮をすることをおすすめします。
ペットにヒガンバナを食べさせないための方法
人間がヒガンバナを食べてしまうケースは少ないですが、犬は好奇心から口に入れてしまうリスクがあるので飼い主が充分気を付けてあげることが大切です。
自宅でペットを飼っているという場合以下の方法でヒガンバナの危険リスクを下げるのがおすすめです。
- ヒガンバナを身近な場所に植えない
- ヒガンバナのある公園や散歩道に立ち入らない
1|ヒガンバナを身近な場所に植えない
ペットを飼っているご家庭の庭でヒガンバナを育てているなら、撤去を含めて管理方法を考える方がよいかもしれません。葉を食べることは無くても地上部に出た球根を口にする可能性はあるので、危険なリスクは先に摘んでおく方が安心できます。
2|ヒガンバナのある公園や散歩道に立ち入らない
愛犬との散歩コースにヒガンバナが無いか事前にチェックしておくことも大事な対策方法。
ヒガンバナは何気ない露地や田んぼのあぜ道などに野生化して生えています。秋の彼岸になると鮮やかな花を咲かせるので、いつもの散歩コースにヒガンバナが自生しているのか意識してチェックしてみて下さいね。
散歩コースを変える必要はありませんが、ヒガンバナが自生している場所で拾い食いなどさせないように気を付けてあげるようにしましょう。
まとめ
今回はヒガンバナの毒性について紹介しました。
- ヒガンバナには植物全体に毒性がある
- ヒガンバナの球根を数百個以上食べないと人の致死量に至らない
- 人間は大丈夫でも体の小さいペットは注意が必要
ヒガンバナは過剰に恐れる必要は無いので、お彼岸に咲く風物詩として見て楽しんでみてはいかがでしょう。
ただ、小型のペットと一緒に暮らしているご家庭は注意してあげるようにして下さいね。


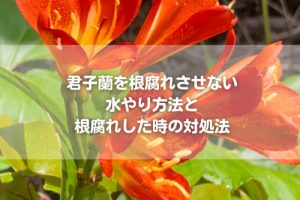



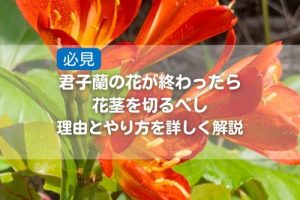

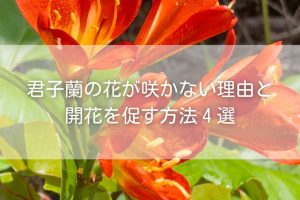

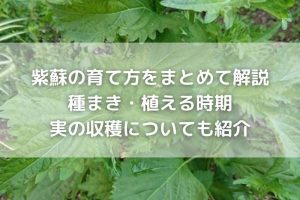

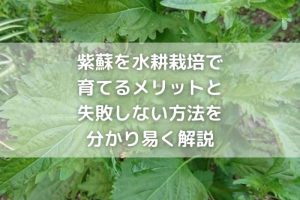

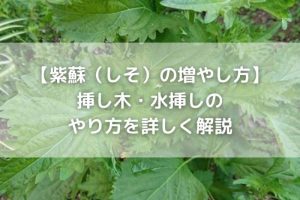

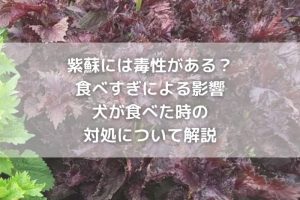
コメント