近年、知名度が上がってきた南国フルーツジャボチカバ。どんな果物なのか興味がある方も多いのではないでしょうか。
ジャボチカバの一番の特徴と言えるのが実の付け方。ジャボチカバは幹に直接実をつける性質があります。
ときには幹が黒く見えるほどに、株全体が沢山の果実で覆われることも・・・。そんな画像を見た人のなかには『ジャボチカバ気持ち悪い』という印象を持ってしまうことも多いそうです。
そんな第一印象の悪いジャボチカバですが、実際の花の様子や味については分からないことも多く、もう少し詳しく知りたいと思っている方は多いと思います。
そこでこの記事ではジャボチカバがどんな植物なのかを知ってもらうために、私自身が実際にジャボチカバを育ててみて『花の様子』や『実を食べたリアルな感想』などをそのまま正直にお伝えしていきます。
- ジャボチカバの開花の様子
- ジャボチカバの結実の様子
- ジャボチカバの収穫目安
- 追熟果なのかどうか
- ジャボチカバがどんな味をしているのか
ジャボチカバの花

普通の樹木が花芽を出すのは主枝から伸びた比較的細い枝に集中します。
ところがジャボチカバの花芽は太くなった幹(主幹)から直接芽吹き、花を咲かせて実をつけます。



ジャボチカバはフトモモ科の植物なのでグァバの花に似たフワフワした柔らかい印象の花を咲かせます。真っ黒な果実のイメージとは全然違いますよね。



ジャボチカバの花が開花すると、それを待っていたかのように小蜂やミツバチといった受粉してくれる昆虫が集まってきます。人工的に受粉しなくても鉢を屋外に置いておくだけで勝手に受粉してくれますよ。
ジャボチカバの実



開花して受粉が成功するとジャボチカバの実の幼果が幹に残ります。それが1~3か月程度かけて少しずつ肥大し、果実も緑色から次第に黒味を帯びてきます。



緑色の幼果の状態だとシワがありしぼんでいるようにも見えますが、果実が段々と肥大していくと皮がパンパンに張っていくので光沢のある立派なジャボチカバの実になっていきます。
ジャボチカバの収穫目安



ジャボチカバの果実は成熟にともなって色が変化していきます。ざっくり言えば『緑色』から『黒色』に変化していくのですが、その途中経過をよく見てみると以下のように変化しているのが分かります。
緑色➡赤みを帯びる➡赤紫色➡黒色(濃い紫色)
なので果実の色が黒くなれば食べ頃とは知っていても、実際には赤紫色の時点で食べてしまっていることも多いです。
完熟した甘いジャボチカバの実が食べたいのであれば、太陽の光を当てて一番色の濃いものを食べてみるのがおすすめです。せっかくなら完熟したものを食べたいですよね。
ジャボチカバの果実を食べた感想|まとめ



自宅で鉢植え栽培しているジャボチカバの実が熟したので味わってみました。
まず皮ごと食べられるのかどうかですが、ジャボチカバの皮には渋み成分が含まれているので皮ごと食べると若干の渋味を感じます。
とはいえ、ブドウの皮ていどの渋味なので気にせず食べることができるレベルです。皮をむいてしまうと皮に多くの果肉がついてしまうため可食部が減ってしまうことから、できれば皮ごと食べるのがおすすめ。



よくジャボチカバの味を『ライチに似た味』とか『カルピスの味』『巨峰味』という風に表現されていますが、私が実際に食べて近いと感じたのは『巨峰』でした。
甘みの強い巨峰の味わいを感じましたね。皮ごと食べましたが渋味もブドウらしさがあり余計に『巨峰』を感じさせる味わいになり、とても美味しく感じました。
ただ、ジャボチカバを食べてみて一つ残念に思うのは『果肉』と『種』の実離れの悪さ・・・。
ジャボチカバの実には種が入っているのですが『果肉』と『種』との実離れが悪いため、種を口から出すと種の周りに果肉がくっついて出てきてしまうんです。
ブドウであれば種を口から出した際、種だけを綺麗に取り出すことができますが、ジャボチカバは種と一緒に果肉も出てきてしまいます。
ブドウよりも種が大きいので可食部が余計に少なくなることは、味は美味しかっただけにチョット残念に感じましたね。
まとめ
今回はジャボチカバがどんな植物なのかを私が育てている株の『開花状態』や『結実状態』を見ながら解説しました。
- ジャボチカバは虫や風の力で受粉可能
- 収穫のタイミングは赤紫色ではなく黒色
- ジャボチカバの実は追熟しない
- ジャボチカバの味は『巨峰』に近い
- 種と果肉の実離れの悪さが残念・・・
ジャボチカバをこれから育ててみたいという方の参考になれば幸いです。


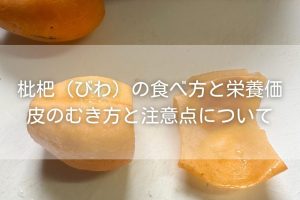

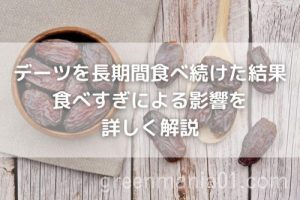

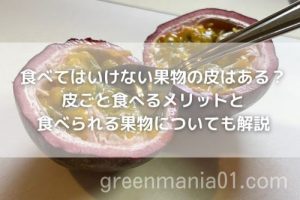

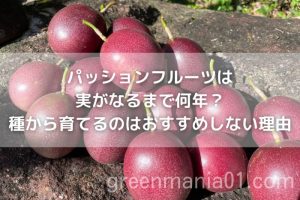

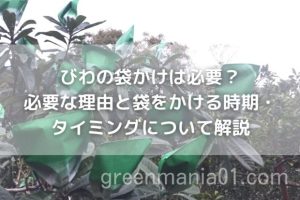

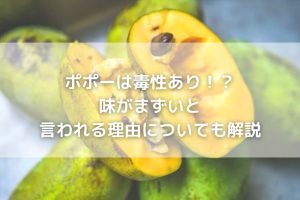




コメント