数十年間、地植えで金木犀を育てていると、金木犀の樹高はかなり大きく成長していると思います。
放任すると樹高が5mを超えるまで成長するため、剪定作業は必須の作業といえます。
今回の記事では金木犀の剪定時期とその方法について詳しく解説しているのでぜひ参考にして下さいね。
金木犀の特徴
| 一般的な呼び名 | キンモクセイ |
| 別名 | - |
| 和名 | 金木犀 |
| 英名 | fragrant olive |
| 学名 | Osmanthus fragrans var.aurantiacus |
| 分類 | シソ目・モクセイ科・モクセイ属 |
| 形態 | 常緑広葉樹 小高木 |
| 大きさ | 4m~18m |
| 開花時期 | 9月~10月 |
| 原産国 | 中国 |
| 日当り環境 | 日なたを好む |
| 耐寒性 | やや弱い |
| 耐暑性 | 強い |
金木犀の名前は木の樹皮が動物のサイ(犀)の足の形状に似ていることから中国で『木犀』と名付けられ、【ギンモクセイ】の白い花色に対して、本種のオレンジ色の花色を金色に見立てたことがこの名前が付けられた由来とされています。
日本には江戸時代に中国から渡来し、その後挿し木によって全国各地に植栽が広まりました。
寒さに若干弱い性質があるため東北南部までが栽培の北限と言われています。
秋にオレンジ色の花が咲くととても甘い香りがあたりに広まります。『ジンチョウゲ』『クチナシ』と合わせて日本の三大芳香木と呼ばれる花木です。
剪定はなぜ必要なの?

そもそも金木犀をなぜ剪定しなければならないのでしょう?
剪定することで以下のような効果が得られるので知っておきましょう。
- 樹体を縮小させる
- 大きく成長させる
- 現状維持させる
1|樹体を縮小させる
枝を強く切り戻すことで、切り口から新たな枝を出させて樹形をまた新しく作り直すことができます。
樹体をコンパクトにすることになるため管理がしやすくなります。
2|大きく成長させる
不要な枝を間引いて切除することにより必要な枝だけが残るので、その必要な枝に栄養が集中させることができます。
その結果、残った枝葉の成長が早くなり樹体を大きく成長させることができます。
3|現状維持させる
1年の成長を見越し、軽く細やかな剪定をすることで毎年同じような樹形を作ることもできます。
極端に小さくも大きくもしたくない方は、毎年樹体サイズが現状維持になるよう定期的に軽剪定しておくと良いですよ。
金木犀の剪定時期について



金木犀を剪定するタイミングは2回あります。
1回目の剪定
1回目は花が終わる11月頃に行います。この作業には花がらに潜んでいるアザミウマ(スリップス)という害虫を繁殖させないために花がらを除去する意味合いも含んでいます。
花が終わったものは樹上から落とすようにしましょう。害虫の繁殖や食害を予防することができますよ。
11月の剪定作業は枝葉をそろえる程度の軽剪定を中心に行いましょう。
あまり枝葉を切り落とし過ぎると、冬越えするためのエネルギーが不足してしまい樹勢が弱まる可能性があります。
強めに樹形を整えるタイミングは次の2回目におこないます。
2回目の剪定
2回目の剪定は、木が春の新芽を出す準備をするタイミングで行いましょう。具体的には2~3月頃が良いです。
冬の寒さも次第に落ち着いてくる時期にあたり、このあと新しい芽を出す準備を整えている時期になります。
大きくなり過ぎた金木犀を切り戻して小さくする場合は、このタイミングに行うようにしましょう。
失敗しない金木犀を強剪定する方法
樹高が大きくなり過ぎた金木犀は強めに剪定を行い自分が管理しやすい高さに切り戻し剪定を行いましょう。
ただ、すべての枝を一度に切り戻ししてしまうと枝葉が失われ過ぎて樹勢が落ちてしまいます。
そのため強めの剪定を行う際には、『外側の枝』と『内側の枝』と1年ずらして強剪定すると良いです。
現状のまま生育する枝を半分ずつ残すことで、剪定後の樹勢低下を防ぐことができるのでお試しください。
まとめ
今回は金木犀の剪定時期・剪定方法について解説しました。
- 剪定には『樹体の縮小』『大きく成長』『現状維持させる』効果がある
- 金木犀を剪定するタイミングは年に2回ある
- 樹体を小さくするのは冬明けしたあとの剪定で行う
- 強剪定は一気に全ての枝で行わずに、1年ごとに分けて行うのがオススメ
金木犀は放任していると巨木に成長するため、剪定作業が必須と言える植物です。
一度に剪定を行おうとすると大変なので、少しずつ手入れしておくことが結構大事になります。
この記事が少しでも参考になれば嬉しいです。


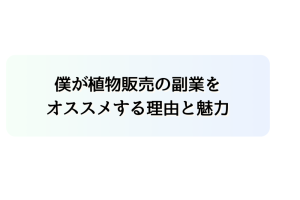

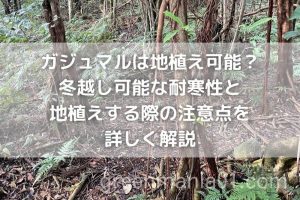

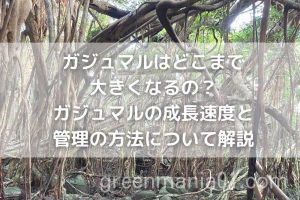



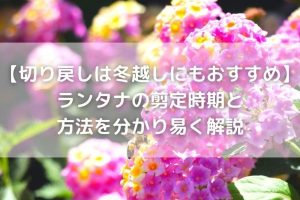

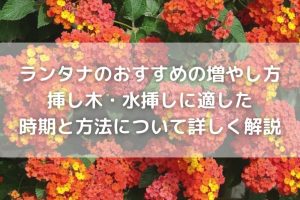

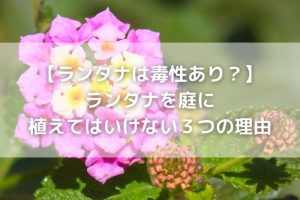

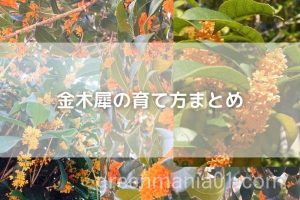
コメント