別の金木犀の株を育てたいと考える方や、これから金木犀を育てるために自分で増やして苗を作りたい方など、金木犀の株を増やしたいという方は多いのではないでしょうか。
今回の記事では金木犀の株をを増やすいくつかの方法について詳しく解説しているので、自分に合ったやり方でぜひチャレンジしてみて下さいね。
金木犀の特徴
| 一般的な呼び名 | キンモクセイ |
| 別名 | - |
| 和名 | 金木犀 |
| 英名 | fragrant olive |
| 学名 | Osmanthus fragrans var.aurantiacus |
| 分類 | シソ目・モクセイ科・モクセイ属 |
| 形態 | 常緑広葉樹 小高木 |
| 大きさ | 4m~18m |
| 開花時期 | 9月~10月 |
| 原産国 | 中国 |
| 日当り環境 | 日なたを好む |
| 耐寒性 | やや弱い |
| 耐暑性 | 強い |
金木犀の名前は木の樹皮が動物のサイ(犀)の足の形状に似ていることから中国で『木犀』と名付けられ、【ギンモクセイ】の白い花色に対して、本種のオレンジ色の花色を金色に見立てたことがこの名前が付けられた由来とされています。
日本には江戸時代に中国から渡来し、その後挿し木によって全国各地に植栽が広まりました。
寒さに若干弱い性質があるため東北南部までが栽培の北限と言われていますが、実際には青森あたりまでは栽培実績があるようです。
秋にオレンジ色の花が咲くととても甘い香りがあたりに広まります。『ジンチョウゲ』『クチナシ』と合わせて日本の三大芳香木と呼ばれる花木です。
金木犀を増やすおすすめな方法はなに?

金木犀を増やす方法として主に3つの方法があります。
- 取り木
- 挿し木
- 接ぎ木
一番気軽に始められるのは『挿し木』ですよね。元気な枝を何本か剪定時に採取しておいて土に挿しておくと発根させることができます。
ただ挿し木の場合太い枝で成功させることが難しいため、どうしても開花するまで時間がかかってしまうのがデメリットなんですよね。
その点、太い枝を苗木としたい場合は『取り木』を活用すると開花も早まるのでおすすめですよ。
ここからは、それぞれの金木犀の増やし方についてご紹介していきます。
金木犀の挿し木について



先述しましたが、挿し木は一番気軽に行える株の増やし方です。
金木犀は樹体が大きくなり過ぎるので、毎年定期的に剪定を行う必要があります。その際に挿し穂を確保しておけばいくらでも挿し木ができるのでぜひチャレンジしてみて下さい。
また、自宅に金木犀の木が無くても友人や知人が所有しているのであれば、お願いして挿し穂を取らせてもらえる気軽さはメリットだと思います。
挿し木は失敗することも多いので、できれば10本以上の挿し穂を準備しておくと良いですよ。
挿し木する前に準備するもの
・挿し穂
・植木鉢
・挿し木用の土(赤玉土など肥料分が含まれていない新しいもの)
・よく切れるハサミ
・割りばしなどの棒(挿し穂を土に刺す時の穴あけ用)
挿し木の手順
金木犀を挿し木にする場合は、以下の手順で行ないましょう。
- 金木犀の親株から挿し穂を採取する
- 採取した挿し穂から出ている白い樹液が、ある程度出なくなるまで洗い流しておく
- 樹液が出なくなったら、水を張った容器に挿し穂を入れて水上げする(約1時間)
- 挿し木用の土に水やりをしてあらかじめ湿らせておく
- 細い棒を使って挿し穂を挿し込むための穴をあけておく
- 挿し穂の切り口部を傷めないように用土に挿し入れ、そっと土を寄せる
- 挿し穂がグラつかないように根元付近の土に圧をかける
ここまで準備ができたら最後に水やりをして、直射日光の当たらない明るい日陰に保管しておきましょう。
生育温度が保たれていれば、だいたい1ヶ月程度で発根します。新芽が出てくれば発根するサインなのでさらに1週間ほど経過したあと鉢上げするようにしましょう。
金木犀の取り木について



取り木は、茎や枝の一部を傷つけその部分を水苔で覆って発根させてから切り取る方法です。
時間はかかりますが、安定して金木犀の株を増やしたいのであれば取り木を試してみて下さい。
取り木は発根したあとで親株から切り離すため、発根できずに失敗してしまっても何度でもチャレンジできるのがメリットです。
また、既に開花している親株から取り木すれば開花までの期間が短く済むこともメリットと言えます。
デメリットはちょっと面倒な点と発根させるまで時間がかかる点。
根が生えるまでは数か月かかるため、こまめに様子を見るようにしましょう。
取り木する際に準備するもの
・よく切れるナイフ
・水苔(水を含ませた状態)
・ラップ
・アルミホイル
・麻紐
取り木の手順
- 水苔を水を入れたバケツに入れて1時間程度浸しておく
- 取り木する枝の樹皮をナイフを使って縦に2~3cm剥がす=環状剥皮
- 水を吸わせた水苔を環状剥皮した部分に団子状に巻き付ける
- 水苔乾燥防止のため、水苔の上から全体をラップで覆い巻き付ける
- 水苔を覆ったラップが外れないよう上下を麻紐で縛る
- 明かりが入らないようラップの上からアルミホイルを被せる
取り木の下準備はこれで完了です。あとはこのまま発根するまでおいておきます。
発根が確認できたらアルミホイルやラップを外してから土に植え付けましょう。
金木犀の接ぎ木について
株の増やし方には『接ぎ木』という方法もあります。
接ぎ木とは植物の一部である枝や芽を切り取って、違う株や違う植物の台木とつなぎ合わせることで、新しい株を養成する方法です。
基本的には早く結実させたい果樹や挿し木・取り木が難しい植物などに用いられますが、金木犀の場合は挿し木も取り木も容易にできるためあまり利用されることは少ないです。
ただ、金木犀が木の根元付近から折れてしまった場合や、樹勢が弱まってしまっている場合は、木を新しく更新するために接ぎ木を試すことはアリだと思います。
金木犀の株を増やす際は一般的に挿し木か取り木を行う人が多いですよ。
まとめ
今回の記事では金木犀の株を増やす方法について解説しました。
金木犀を増やす方法は『取り木』がおすすめです。時間はかかりますが確実に発根させることができ、太い枝でも成功させることができます。
太い枝で苗木が作れれば、花が咲き始めるまでの期間も短くて済むのでメリットは大きいです。
ぜひこの記事を参考に金木犀の取り木にチャレンジしてみて下さいね。


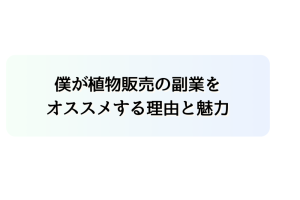

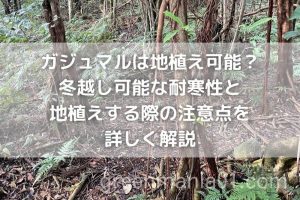

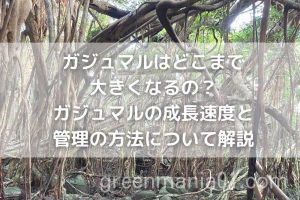



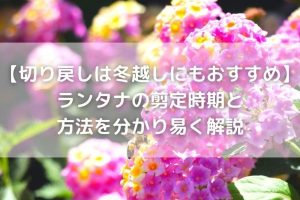

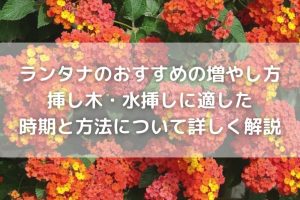

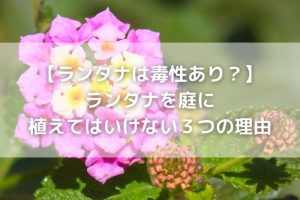

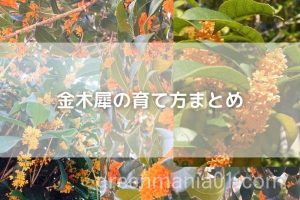
コメント